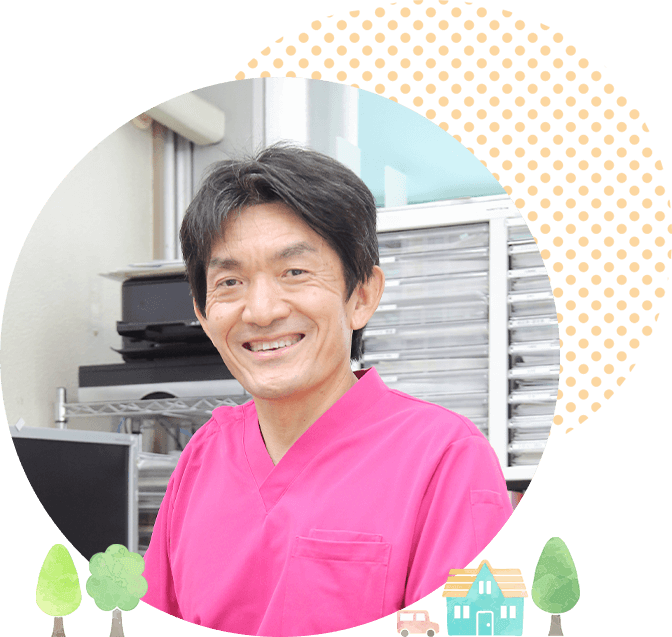「最近ずっと疲れやすい」「喉がやけに渇く」「夜中にトイレで何度も起きる」。
こうした体の変化は、忙しさのせいにしてしまうかもしれません。しかし、糖尿病の初期症状としてよく見られるサインでもあります。
糖尿病は、自覚が乏しいまま進むことが多いため、早い段階で「気づくこと」が何より大切です。今回は、糖尿病の初期症状と原因、そして受診時に役立つ検査の見方までわかりやすく解説します。
■だるさ・口渇・多尿…それ、糖尿病の初期症状かも
血糖の上昇が緩やかな場合、しばらくは自覚症状がほとんど出ないことも珍しくありません。一方で、血糖が高い状態が続くと、体は少しずつ異変を発し始めます。その小さな変化を生活の中で拾えるかどうかが、合併症を遠ざける第一歩です。
◎初期症状はなぜ気づきにくい?“無自覚のまま進行”する怖さ
糖は本来、体のエネルギー源ですが、インスリンの作用不足で細胞に取り込めないと、血液中に余った糖が増えます。ところが、この変化だけでは痛みも発熱も起きません。そのため「なんとなく調子が悪い」程度で見過ごされがちです。
自覚がないまま生活を続けると、高血糖がじわじわと血管や神経を傷つけ、気づいた時には合併症が進んでいた、ということもあります。
◎糖尿病の三大初期症状「口渇・多尿・体重減少」
血糖が高いと、腎臓は余分な糖を尿に出そうと働き、尿の量や回数が増える(多尿・頻尿)ようになります。水分が失われるため強い喉の渇き(口渇)を感じやすくなり、夜間のトイレも増えるのが一般的です。
糖をうまくエネルギーにできないため、体は脂肪や筋肉を分解して補おうとして体重が急に減ることがあります。
◎見逃されがちな“軽い変化”も初期サインの可能性がある
-
「だるさが抜けない」
-
「食べてもすぐお腹が空く」
-
「目がかすむ」
-
「皮膚が乾燥してかゆい」
-
「傷が治りにくい」
-
「手足の先がチクチクする」
こうした変化も、初期症状として見られることがあります。必ずしも糖尿病とは限りませんが、複数が続く場合は早めに検査を受けて確認しましょう。
◎症状が出たら何をすべき?放置によるリスクとは
「様子を見る」よりも、「数値で確かめる」ことが肝心です。放置すると、目(網膜)、腎臓、神経などの細い血管に障害が進み、視力低下や腎不全、しびれ・痛み、足の潰瘍などにつながるかもしれません。
動脈硬化が進むと心筋梗塞や脳梗塞のリスクも上がります。早期の受診と生活の見直しで、これらの流れは遅らせることができます。
■糖尿病はなぜ起こる?原因を知っておこう
糖尿病の原因は一つではありません。体質(遺伝的素因)に、食べ過ぎ・運動不足・肥満・ストレス・加齢などの環境因子が重なることで発症リスクが高まります。加えて、1型と2型では背景が大きく異なります。
◎インスリンと血糖の関係を知ろう|糖尿病のしくみ
インスリンは膵臓から分泌され、食後に上がった血糖を細胞へ運ぶ“鍵”の役割をします。糖尿病では、インスリンの量が足りない、またはインスリンが効きにくい状態が起こり、血糖が慢性的に高くなります。
◎1型と2型で異なる原因とは?体質・生活習慣・自己免疫の違い
1型糖尿病は、自己免疫などの影響で膵臓のβ細胞が壊れ、インスリンをほとんど作れなくなります。年齢を問わず発症し、インスリン補充が必須です。
2型糖尿病は、糖尿病の大多数を占め、体質に生活習慣の乱れや加齢が重なって、分泌低下と抵抗性が少しずつ進むタイプです。中高年に多い一方、若い人でも発症することがあります。
◎生活習慣がカギになる2型糖尿病|食事・運動・ストレスが影響
過剰な摂取エネルギーや内臓脂肪の増加、長時間の座位、睡眠不足や強いストレスは、インスリン抵抗性を悪化させます。体重が標準でも、運動不足や偏った食習慣が続けばリスクは上がります。
◎糖尿病になりやすい方の特徴は?
-
家族に糖尿病がいる
-
40歳以上
-
体重増加が続いている
-
運動不足が長い
-
高い血圧やコレステロールや中性脂肪が高い
こうした条件が重なるほど発症しやすくなります。リスクを自覚したら、数値で現状を把握し、生活を整えることが予防への近道です。
■糖尿病の疑いがあるときに見るべき“数値”と検査のポイント
「症状があるかないか」に加えて、「検査でどうだったか」という数値は、診断と経過観察のポイントです。代表的な検査と見方を、受診前の予備知識として押さえておきましょう。
◎空腹時血糖値・HbA1c・尿糖検査で何がわかるのか
-
空腹時血糖値(FPG)
10時間以上の絶食後に測る血糖です。一般に126 mg/dL以上なら糖尿病が強く疑われ、110〜125 mg/dLは境界域(予備群)の目安になります。
-
HbA1c
過去1〜2ヶ月の平均的な血糖を反映し、6.5%以上なら糖尿病が強く疑われます。
-
75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)
ブドウ糖を飲んで2時間後の値が200 mg/dL以上だと糖尿病型、140〜199 mg/dLは境界域です。
-
尿糖
高血糖で尿に糖が出ていないかを調べますが、一過性に陽性化することもあるため、血液検査と合わせて評価します。
◎どこまでが正常?予備群との境界ラインを知っておこう
正常の目安は、空腹時血糖が110 mg/dL未満、OGTT2時間値が140 mg/dL未満です。この範囲には入らないが、糖尿病ほど高くない状態が境界型(糖尿病予備群)になります。
放置すると糖尿病に進むリスクが高いため、食事・運動・睡眠など生活の立て直しと、定期的な数値チェックが重要です。
■糖尿病は“気づいたとき”が治療の始めどき
初期症状はささやかでも、体は確かなサインを出しています。思い当たる点があれば、数値で確認しましょう。原因の中心にあるインスリンの「量」と「効き」を乱す生活要因は、見直すことで改善できます。
糖尿病は、早く見つけて正しく向き合えば、合併症を遠ざけ、日常を守れる病気です。体のサインに気づいたら放置せず、まずはご相談ください。