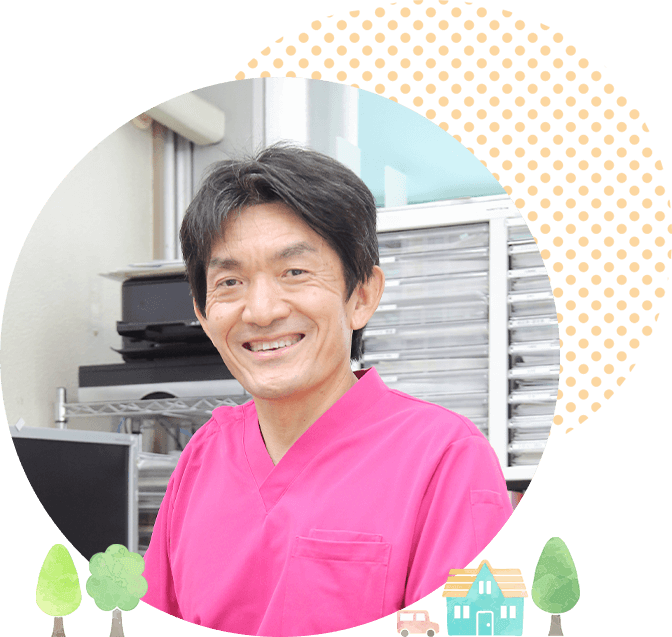糖尿病と診断されたとき、多くの方がまず気になるのは「この病気は治るの?」「ずっと薬を飲み続けるの?」ということではないでしょうか。
2型糖尿病は、生活習慣と深く関係しており、食事や運動、薬によって血糖値をうまくコントロールすることが重要です。
ここでは主に2型糖尿病について解説していきます。
糖尿病の基本的な治療方法や薬の種類、それぞれの特徴と注意点をわかりやすく紹介していきますので、糖尿病と上手につき合っていくための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
目次
■糖尿病は治る病気? それとも一生つき合う病気?
糖尿病は「完治」という意味では現時点で難しい病気になります。しかし、治療と生活改善により血糖値を安定させ、合併症のリスクを下げることは十分に可能です。
体重や食事、運動を見直すことで薬が少なくなったり、いったん不要になる「寛解」に近い状態を保てる方もいます。大切なのは、早めに治療を始め、続けやすい方法で血糖コントロールを積み重ねることです。
※寛解:医師の指導のもとで薬の量を減す・薬を使わずに血糖値が安定している状態
■治療の第一歩はここから!糖尿病の基本3本柱
糖尿病治療は食事療法・運動療法・薬物療法の三本柱で成り立ちます。まずは生活習慣を整え、それでも目標に届かない場合に薬を組み合わせます。
◎食事だけじゃない!なぜ運動療法が効果的なのか
運動をすると筋肉が糖を取り込みやすくなり、食後の血糖上昇を抑えられます。続けるほどインスリンの効きが良くなり、中性脂肪の低下や善玉コレステロールの上昇、血圧の改善も期待できます。
◎「薬=最後の手段」ではない?薬物療法が必要になる理由
食事の改善と運動を2〜3ヶ月続けても目標に届かない場合、薬物療法を検討することがあります。薬は「頑張りが足りないサイン」ではなく、生活習慣の改善を優先しながら、必要に応じて薬を併用することで血糖を管理する方法です。
■薬で血糖値を下げる仕組み
血糖を下げる「薬(飲み薬・注射)」には、作用の違いによっていくつかのタイプがあります。どれが合うかは体質、合併症、生活パターンで変わるため、薬の調整は自己判断ではなく、医師との相談のうえで検討しましょう。
◎膵臓に働きかけてインスリンを出すタイプの薬
スルホニル尿素(SU)薬や速効型インスリン分泌促進薬は、膵臓を刺激してインスリン分泌を助けます。食後の高血糖に効きやすい一方、低血糖や体重増加に注意が必要です。
DPP-4阻害薬は、食後に分泌される「インクレチン」の働きを長持ちさせ、血糖が高い時にだけ分泌を後押しするため、低血糖が比較的少ないのが特徴です。
◎インスリンの効きをサポートする薬にはどんな種類がある?
ビグアナイド薬(代表はメトホルミン)は肝臓からの糖の放出を抑え、体のインスリン感受性を高めます。体重が増えにくい利点があり、第一選択薬になることが多い薬です。
チアゾリジン薬はインスリンの効きを強めますが、むくみや体重増加に注意します。イメグリミンは、膵臓の働きとインスリン感受性の双方を支える作用を持ちます。
◎糖の吸収・排出を調整して血糖値を抑える薬のちから
α-グルコシダーゼ阻害薬は、腸で糖の吸収をゆっくりにして食後の急上昇を抑えます。ただし、お腹の張りなどが出ることがあります。
SGLT2阻害薬は腎臓で糖の再吸収を抑え、尿と一緒に余分な糖を出す薬です。体重や血圧の低下が期待できる一方、脱水や尿路・性器感染のリスクに注意する必要があります。
◎GLP-1受容体作動薬とは?注射薬との違い
GLP-1受容体作動薬はインクレチンの作用を直接高め、食欲を抑える効果も期待できます。低血糖が少ない一方、吐き気・胃もたれなどの消化器症状が出ることがあります。
インスリン注射は、飲み薬や他の注射で十分に下がらない場合や、感染症・手術時、腎機能低下や妊娠希望など特別な状況で用いる治療法です。自己注射は皮下に打つ方法で、手順は慣れれば難しくありません。
■薬を使うなら知っておきたい!副作用と注意点
薬の強みと弱みを知っておくと、安心して長く続けられます。体調の変化や検査値の推移は、受診のたびに共有しましょう。
◎気をつけたい「低血糖」…どんな症状?どう防ぐ?
冷や汗、手のふるえ、動悸、強い空腹感は低血糖のサインです。意識がはっきりしているなら砂糖やジュースなどを少量摂取し、α-グルコシダーゼ阻害薬を飲んでいる場合はブドウ糖を摂りましょう。食事の量や時間、運動とのバランスを崩さないことが予防につながります。
◎吐き気やむくみ、体重増加…薬ごとの副作用を理解しよう
-
メトホルミン:下痢や胃もたれが出やすい
-
SGLT2阻害薬:脱水や感染症に注意
-
チアゾリジン薬:むくみや体重増加
-
SU薬・速効型薬:低血糖のリスク
-
GLP-1受容体作動薬:吐き気や便秘
異変を感じたら自己中断せず、必ず主治医に相談しましょう。
◎薬の見直しや変更が必要になるのはこんなとき
-
妊娠希望や妊娠中
-
腎臓・肝臓の機能低下
-
ステロイドなど高血糖を起こす薬の使用
-
発熱や感染症
-
手術前後
これらの場合は、治療の組み立て直しを行います。運動療法を強めるときも、低血糖予防のために薬の量を調整する場合があります。
■予防こそ最大の治療!糖尿病にならないために
予防は今日から始められます。体重を適正に保ち、主食・主菜・副菜をそろえた食事を心がけ、夜遅い食事や欠食を避けてください。睡眠不足やストレスも血糖を押し上げるため、生活リズムを整えることが重要です。
◎薬に頼らない体をつくる生活習慣とは
短時間でも毎日体を動かし、座りっぱなしを避けましょう。食事は野菜や海藻、きのこを先にとって血糖の急上昇を抑え、よく噛んでゆっくり食べてください。アルコールや間食は量と頻度を見直し、体重の少しずつの減少を目標にしましょう。
◎糖尿病は早期発見で差がつく!定期検査が大切
年に1回の健診で空腹時血糖やHbA1cを確認しましょう。体重が増えた、疲れやすい、のどが渇く、尿の回数が増えたといった変化があれば早めの受診が安心です。
■糖尿病は「治す」のではなく「コントロール」する
糖尿病は、治る?と不安になる病気ですが、治療・食事・運動・薬を上手に組み合わせれば、合併症を遠ざけながら普通の生活を送ることもできます。目標は「完璧」より「続けられること」です。
まずは、ご相談ください。一緒に無理なく予防とコントロールを積み重ねていきましょう。