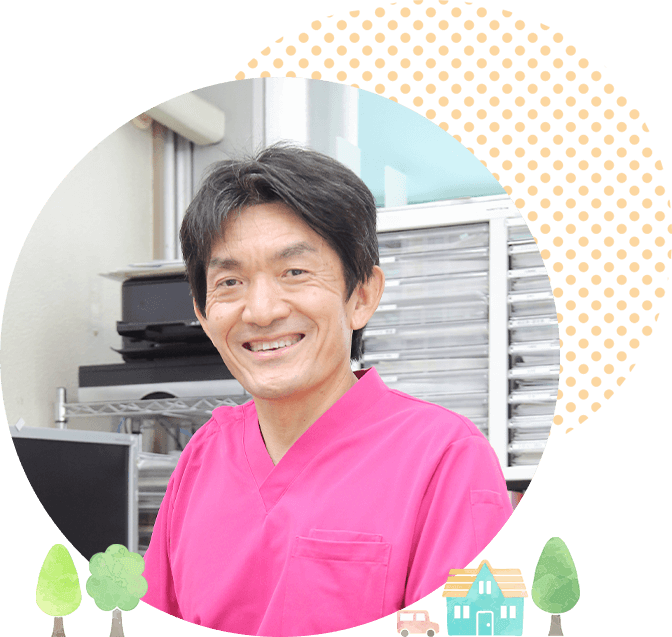毎年流行するインフルエンザに備える現実的な手段がワクチンです。今回はインフルエンザの効果、適切な接種時期、年齢別の回数や副反応・費用までわかりやすく説明します。
目次
■インフルエンザワクチンの効果は?
インフルエンザは毎年流行する呼吸器感染症です。体の免疫をあらかじめ準備しておくことで、かかった場合のダメージを減らすことを狙います。
◎発症を防ぐ?重症化を防ぐ?気になるワクチンの「効果」
ワクチンの効果は「万能」ではありません。年や型の一致度によって発症予防効果は変動しますが、重要なのは重症化を防ぐ効果です。
基礎疾患のある方では、気管支炎・肺炎・脳炎などへの進行リスクを下げ、入院や重症化を減らす効果が確認されています。小児でも、流行シーズンの欠席や家庭内感染の連鎖を抑える観点でメリットがあります。
◎ワクチンの効果はどのくらい続く?持続期間とピークを知ろう
接種後すぐにインフルエンザから守られるわけではありません。免疫が立ち上がるまでおよそ2週間、実用的なピークは3〜4週間前後と考えられます。その後はゆっくりと低下していきますが、一般に5〜6ヶ月程度は一定の有効性が見込めます。
■インフルエンザの予防接種は「いつから」?接種時期の目安
医療機関での接種は10月ごろからスタートします。
◎予防接種の開始時期は10月頃から
供給が始まるのが10月頃で、予約もこの時期から動きます。毎年ウイルスは変異し、ワクチンの内容もシーズンごとに更新されます。そのため毎年の接種が必要です。
◎適切な接種時期は11月上旬までが目安
本格流行は12月中旬〜1月に入りやすいのが通例です。効果のピークが接種後数週間で来ることを踏まえると、11月上旬までに1回目を終えておくと安心です。年によって流行入りが早まることもあるため、ニュースや自治体情報を確認し、前倒しも検討しましょう。
◎効果が出るまでに時間がかかるため、早めの接種が安心
接種直後は十分な免疫ができていません。「受けたのにかかってしまった」というケースは、接種直後〜2週間以内に感染した可能性もあります。園や学校、職場のイベント時期や帰省予定なども加味して、早めにスケジューリングしましょう。
■インフルエンザワクチンの種類について
注射の「不活化ワクチン(インフルエンザHAワクチン)」に加えて、2024年度から「点鼻の生ワクチン(フルミスト®:経鼻弱毒生インフルエンザワクチン)」が使えるようになりました。どちらも効果がありますが、対象年齢や接種回数、注意点が異なります。
※点鼻タイプの「フルミスト®」は当院では取り扱っていません。
不活化ワクチンでの接種をご案内します。
■インフルエンザワクチンは何歳から打てる?
生後6か月(満6か月)から接種可能です。6か月未満では免疫が成熟しておらず、十分な効果が期待しにくいとされています。
◎生後6か月未満の赤ちゃんのインフルエンザワクチンは避ける
家族や同居人がワクチンを受けること、流行期には不要不急の外出を控えること、手洗い・咳エチケットを徹底することが、家庭内感染を減らす実践策になります。
◎6か月〜1歳未満はどうする?
6か月〜1歳未満の月齢では一定の効果は見込めますが、免疫がまだ未熟なため得られる効果に個人差があります。地域の流行状況、家族構成(きょうだいの在園・在学状況)と合わせ、かかりつけ医と相談して接種可否やタイミングを決めましょう。
◎1歳以上は集団生活スタートの節目
外出や集団生活が増える1歳以降は、保育園・幼稚園に通うお子さんや、兄弟間の伝播が心配な家庭で接種の意義が高まります。
■インフルエンザワクチンの「接種回数」は?年齢で異なる
ワクチンは注射の不活化ワクチンで、体内に「記憶」をつくるための刺激を1回または2回に分けて与えます。
◎子どもは2回、大人は1回?年齢別の接種スケジュール
6か月〜13歳未満は、原則2回接種が推奨されます。一般には4週間前後の間隔をあけるのが目安です。
一方、13歳以上は過去の感染・接種で免疫があるため1回接種でも一定の抗体上昇が得られます。なお、医師の判断で回数や間隔が調整されることもあります。
◎1回目は11月上旬までが安心。理由はワクチンの立ち上がり
抗体が十分に上がるまで約2〜4週間かかるため、流行が本格化する前に1回目、小児は2回目がピークに間に合うよう逆算して組み立てます。
◎他のワクチンと一緒に打っても大丈夫?同時接種と注意点
インフルエンザワクチンは他の不活化ワクチンや生ワクチンとの同時接種が可能です。原則として接種間隔の制限はなしですが、注射の生ワクチン同士を別日に打つ場合は27日以上空ける取り決めがあります。
■ワクチンの「副反応」はある?接種前に知っておきたいこと
どのワクチンにも副反応の可能性はあります。
◎よくある副反応:腫れ、痛み、発熱など
接種部位のはれ・痛み・赤み、だるさ、微熱などが代表的です。多くは数日で自然に改善します。患部を清潔に保ち、入浴は可能です。強い痛みや高熱が続く場合は医療機関に相談してください。
◎重篤な副反応は稀だが、注意が必要な場合とは?
ごくまれにアレルギー反応(じんましん、息苦しさ、ふらつきなど)が起こることがあります。接種後30分程度は院内で様子観察が推奨されるのはこのためです。明らかな体調不良がある日は無理せず延期しましょう。
◎卵アレルギーがあっても基本的に接種可能
インフルエンザワクチンは卵由来成分が極めて微量で、精製の進歩により卵アレルギーでも多くの方が接種可能です。迷ったら必ずかかりつけ医に相談してください。
■ワクチンの「費用」は?自己負担になる場合も
インフルエンザワクチンは任意接種で、一般的に3,000円〜5,000円程度です。費用は医療機関や自治体の補助制度により異なります。
◎子どもや高齢者で補助がある自治体も
自治体ごとに対象年齢、自己負担額、実施期間が違います。母子健康手帳や自治体サイト、広報紙をチェックし、必要書類や期間を逃さないようにしましょう。
◎任意接種のため、医療機関によって異なる
同じ地域でも医療機関で料金が異なることがあります。家族で受ける場合は、同日接種の可否や予約枠、キャンセル規定も合わせて確認しておくとトラブルを防げます。
■インフルエンザワクチンは誰が「優先」して受けるべき?
合併症リスクが高い層では優先度が高いと考えましょう。
◎乳幼児、高齢者、基礎疾患のある方
6か月以上5歳未満、65歳以上、慢性呼吸器・心血管疾患・糖尿病・腎疾患・肝疾患、神経筋疾患、免疫抑制状態などの方は、流行前に計画的な接種が重要です。
◎妊婦や医療従事者、介護職も積極的な接種を
妊娠中は母体の重症化予防に加え、出生直後の赤ちゃんの感染リスク低減にもつながります。医療・介護に従事する方は、自身の防御と同時に周囲への感染拡大防止の観点からも接種が推奨されます。
◎子どもが多く集まる保育園・学校でも早期接種を
園や学校など集団生活の場では流行期の波が早く立ち上がることがあります。行事予定も踏まえ、11月上旬までの1回目完了をひとつの目安として、園児・児童・きょうだいでそろえて接種計画を立てると効果的です。
■インフルエンザワクチンは家族と自分を守る現実的な予防策
ワクチンは万能ではないものの、重症化や入院のリスクを小さくすることができます。効果発現まで約2週間かかるため、流行前の計画接種が安心です。気になることがあれば、まずはご相談ください。